「作品を展示することに意味を見出せない」という増本泰斗。美術館で行う展覧会ではない、ある特定の地域で行われる芸術祭は、その土地に影響を与えるがゆえに、そのあり方に疑問を持つと言います。現代美術では最も歴史が古く権威のあるベネチア・ビエンナーレやその他のアートフェスティバルは、原子力発電所や米軍基地と同じ問題を抱えると考え、作品のタイトルにした増本。
作品は土湯温泉町に展示せず、ウェブ媒体にのみ限定しています。アラフドアートアニュアルは原発の抱える福島で行う芸術祭です。芸術祭は不要なのでしょうか。増本はアラフドアートアニュアルに対してどのような表現を行うのでしょう。ディレクターとアーティストは定期的に話し合いを持ちながら、作品のあり方を探りました。
作品サイト:http://biennaleasnuclearplants.tumblr.com/
増本泰斗|Yasuto Masumoto
1981年広島県生まれ。2007年〜2008年ポルトガル・リスボン在住。現在は、京都に住んでいる。Grêmio Recreativo Escola de PolíticaとThe Academy of Alter-globalizationを主宰。また、美術批評家の杉田敦との共同企画Picnicを行なっている。最近の主な活動は、予言と矛盾のアクロバット、ドローイング、本の制作、非常勤講師、ARTISTS’ GUILD。
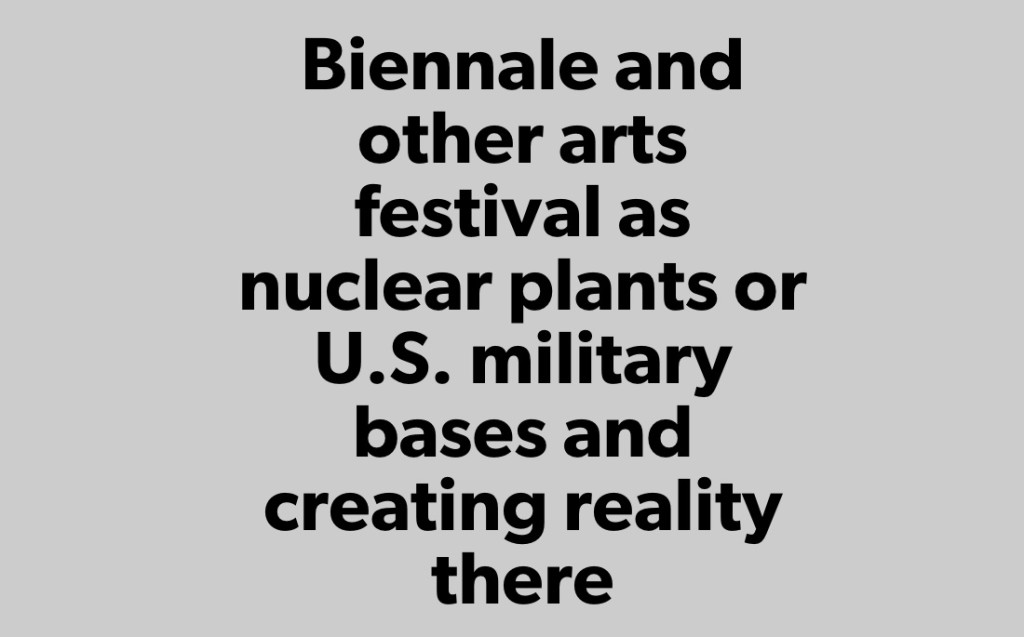
『Biennale and other arts festival as nuclear plants or U.S. military bases and creating reality there』ウェブサイト画面
何かを理解するうえで「そこに行く/行ったということ」をまず重要視する姿勢を危惧しています
メディアアート専攻写真領域修了されていますが、それらの技術的手法または思考法は、作品にどのような影響を与えていますか?
大学院生の頃、研究室にいると、ランチには必ず担当教授が近くの美味しい寿司屋の出前をとってくれて、テクノロジー、写真産業、アート、食べ物の話に花を咲かせていました。影響があるとすれば、そうした会話だと思います。
現在の表現方法に至った経緯を教えて下さい。
映像や、既成品を使うこと以外に、パフォーマンス、写真、ドローイング、イベント、コラボレーション、授業、本、WEB、テキスト、洋服、パーティーなど、様々な手法で制作しています。言えば、そのとき、ふつふつと考えていたことを実験するために、たまたまその手法を使ったということぐらいで、もはや、気分で選択したとしか言いようがありませんが、とりあえず選択した手法を試みることで、自分自身が何を得て、何を失ったかに興味があります。
リスボンや東京、現在は京都に住んでいますが、それぞれの土地はアーティストにどのような影響を与えましたか?
数ヶ月前に、知人と飲んでいて、今までやってきた「アルバイト」についての話になりました。「土地」の話もよいですが、その土地で行った「アルバイト」の話がしたいです。つまり、ある土地で生計をたてるための労働がアーティストであることにどのように影響を与えるかということです。その観点から考えると、僕の場合は、その時々の労働が直接的にアート活動に影響を与えているように感じます。いやむしろ、生計を立てる労働とアート活動は不可分である。みたいに感じています。
出品作「Biennale and other arts festival as nuclear plants or U.S. military bases and creating reality there」について、ウェブ媒体での発表にした経緯を教えて下さい。
なんとなくWEB媒体が良いと思っただけですが、後から思うのは、例えば、海外の行けない展覧会などの画像や動画をウェブ媒体を介して見ること。そして、時に、行ったつもりになって見たり考えたりしているときがあること。そこに惹かれたんだと思います。反対に、何かを理解するうえで「そこに行く/行ったということ」をまず重要視する姿勢を危惧しています。でも行かなきゃ分からないこともいっぱいあるんですけど。。。いずれにせよ、行ったつもりになるということと、今回テーマに掲げたことは親和性が高いと思いました。
地域振興の視点から、芸術祭と原発や米軍基地問題を同じようなものとして自覚することをテーマにしていますが、増本さん自身が考える「地域」とはどういうものなのでしょう?
住んでいる地域のことを想います。同時に、行ったところのある地域を想います。そして、行ったことがない地域を想います。ただ、地域とはどういうものか?という問の岐路にあるのは何なんだろうといつも考えます。例えば、地域、そのイメージは、個々人固有のものであり、地域とはそれらがモザイク状に集まったものである。つまりバラバラなものの寄せ集めであり、その境界は非常に曖昧なはずです。
しかし、地域とはどういうものか?という問を掲げることで、なんとなく輪郭を浮かび上がらせようとする力が働いていくように感じています。僕はむしろ、なんとなく想起できる地域がなんとなく想起できない地域と置換え可能な状態を考えています。つまり、ある地域は別の地域でもあるということです。テーマの裏側にあるのはそうした意識です。
ありがとうございました。interviewer:yumisong